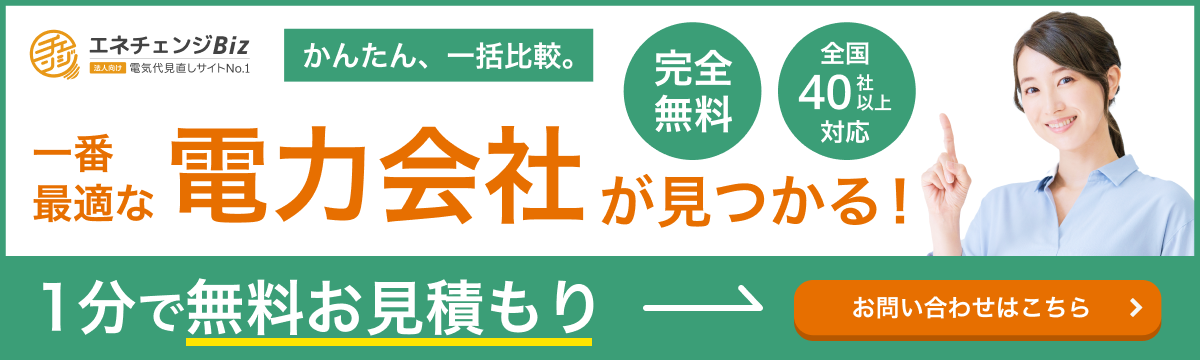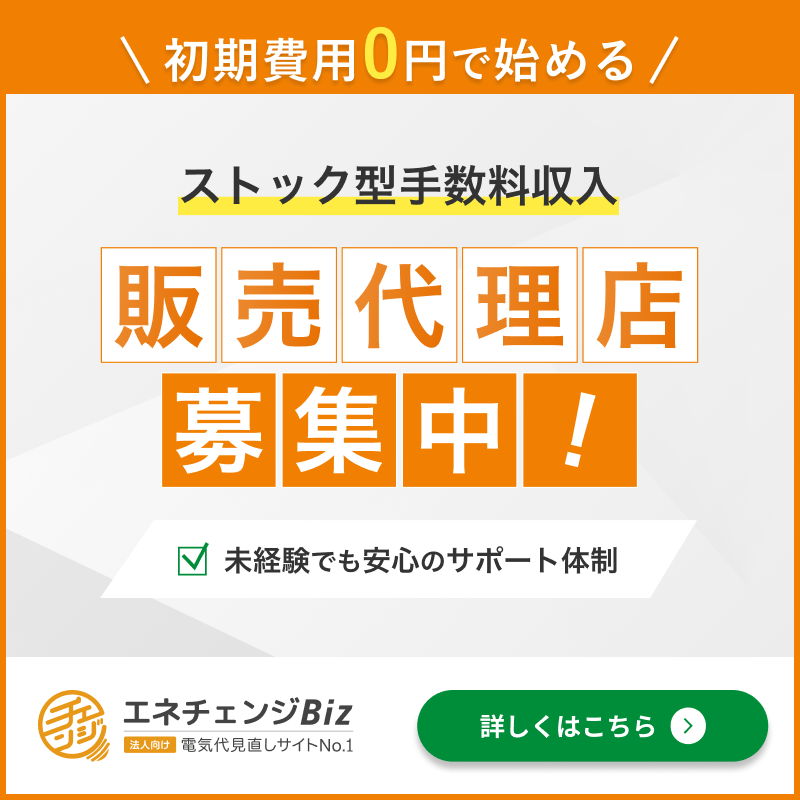※編集部注:【2024年3月14日更新】電気代の値上げが叫ばれる昨今。市場連動型プランという比較的新しいメニューが登場し、これからの普及が期待されています。本記事では、法人向けの市場連動型プランの概要や従来メニューとの違い、普及の背景、メリットやデメリット、よくあるご質問を紹介していきます。
市場連動型プランとは:固定単価メニューとの違い
多くの法人が契約する高圧電力では、直近12カ月の電力使用の最大値に応じた基本料金と使った分だけ増える電力量料金(従量料金)が固定単価で計算され、再生可能エネルギー発電促進賦課金と燃料費調整額が加わるメニューが一般的でした。
今回ご紹介する市場連動型プランは、日本卸電力取引所(JEPX)の取引価格に連動して価格が決まるメニューです。料金計算方法や市場価格の反映方法は各社で異なりますが、電力量料金が固定単価ではなくなるケースや、電源調達費という項目が追加されるケースがあります。

市場連動型プランの仕組み
市場連動型プランでは、電力市場の価格変動に応じて料金が決定される仕組みとなっています。つまり、市場の価格が低い時には電気料金も安くなるのです。
例えば、昼間などFIT太陽光が市場に流れる時間帯や休日などの電力需要が低い時間帯は市場価格も低くなります。この時間帯に電力を多く使用する場合、固定価格のメニューと比べて電気料金が安くなる傾向があります。
その他、晴天で太陽光発電による電力供給量が多くなる日や時間帯は市場価格が安くなりますし、空調使用などにより電力需要の多い真夏日や真冬日は市場価格が高くなります。つまり市場連動型プランでは、季節や気温、時間帯によって変動する市場価格に合わせることで、電気代を安くすることが出来るのです。
また、日本卸電力取引所では、北海道・東北・東京・中部・北陸・関西・中国・四国・九州の9つのエリアで電力取引を行っています。この地域ごとの市場価格をエリアプライスと言います。市場連動型プランではエリアプライスを採用しているため、地域によって30分ごとに価格が変動するという特徴があります。
このように常に市場価格の変動を受ける市場連動型プランですが、電力市場の推移をチェックしながら省エネを図る企業様もいらっしゃいます。毎日の電力市場は下記サイトから確認可能です。
参考:エネチェンジインサイトマーケット
家庭向けの市場連動型プランに関心をお持ちの方は、こちらをご覧ください。
日本卸電力取引所(JEPX)とは
日本卸電力取引所(JEPX)は、日本で唯一の卸電力取引市場を開設・運営する取引所です。市場連動型プランで用いられる「市場」とは、この日本卸電力取引所(JEPX)のことを指しています。
2000年から始まった電力自由化によって、新電力が電力小売事業に新規参入しました。しかし新電力の多くは自社所有の発電所がなく電力を購入する必要があります。そのため、2003年に電力を扱う卸市場として日本卸電力取引所(JEPX)が誕生しました。
日本卸電力取引所(JEPX)では、電力会社間で電力の入札・売買がされています。1日を30分ごとに分割した48コマで取引が行われており、各コマごとに取引価格が変わります。各電力会社は電力需要に応じて、自社で仕入れている電源に不足が生じた場合、必要な電力量を入札・購入します。逆に余剰が生じた場合は入札・売却します。
また市場価格の動き方について、温暖な気候等で電力需要が少ない季節や、晴天で太陽光発電による電力供給量が多くなる日や時間帯は市場価格が安くなり、空調使用などにより電力需要の多い真夏日や真冬日は高くなる傾向があります。

2023年のスポット市場価格の30分ごとの最安値は0.01円、最高値は52.94円でした。このグラフは全国平均市場価格ですが、市場価格は電力エリアによって異なるため、市場連動型プランの料金計算時には各電力エリアの市場価格が適用されます。
法人向け市場連動型プランの普及理由と今後
電力会社が市場連動型プランを始める理由
今までは家庭も法人も、基本料金と使用した電力量で電気料金が決まるプランが一般的で、単価は固定されていました。
しかし、昨今は世界情勢の影響を受けて、電源となる石油や石炭、液化天然ガス(LNG)が高騰しています。そのため、多くの小売電気事業者にとって発電事業者から仕入れる電力原価の価格が高騰し、固定単価で販売する方法では採算が取りづらくなっています。その結果、需要家へ値上げを迫る(あるいは事業撤退する)ケースが増えました。
参考:値上げ注意。 最終保障供給約款に契約する法人が気をつけるべきこと
こうした市況の変化を受けて現れたのが市場連動型プランです。新電力のうち、家庭向けは株式会社ハルエネ(ハルエネでんき)などが、法人向けは日本テクノ株式会社(環境市場でんき)などが提供を始めていました。
旧一般電力事業者にも期待がかかる中で、口火を切ったのは中部電力でした。2022年5月20日、同社グループ会社である中部電力ミライズ株式会社では、地域内の法人需要家に対して、市場連動型プランの申し込み受付再開を発表しました。
参考:法人の電気料金の値上げ・高騰を徹底解説。電力会社の適切な比較、見直し方法は?
今後、市場連動型プランは一般的になるのか
市場連動型プランが始まった背景は先述した通りですが、同プランは法人の需要家に受け入れられ、今後もっと広がりをみせていくのでしょうか?
電力価格について直近の経済産業省のデータを振り返ってみます。2022年秋から年末にかけて概ね20〜30/kWh台で推移していたものの、2023年度前半の平均価格は燃料価格の低下等を背景に10.14円/kWhとなっています。一方、2023年9月20日には今年度のシステムプライス(コマ単位)の最高値52.94円/kWhを記録するなど、燃料価格高騰や円安の影響による変動が見られます。
新たな原子力発電所の稼働準備が進められており、運転開始がされた場合は、供給力が増加することで市場価格の安定化が見込まれます。市場価格の安定化が見込まれる場合は、需要家にとってメリットが出る可能性も見込まれ、多数ある電力メニューの一つの選択肢として市場連動型プランの適用も一般的になると推察します。
法人向け(高圧)市場連動型プランを提供する電力会社一覧
法人向け(高圧)の市場連動型プランを提供している主な企業をご紹介します(公式サイトやプレスリリースなどで公表せずに提供を開始している企業もあると考えられます)。
- 一部の新電力(日本テクノ株式会社、株式会社afterFIT 、株式会社U-POWER、シナネン株式会社ほか)
- 一部地域の大手電力(2023年12月18日更新時点)
| 事業者名 | 供給開始時期 | 市場連動型プランの受付ページ |
| 東北電力株式会社 | 2022年7月 | |
| 東京電力エナジーパートナー株式会社 | 2022年8月 | あり |
| 中部電力ミライズ株式会社 | 2022年6月 | 専用ページはなし |
| 北陸電力株式会社 | 2022年8月 | 専用ページはなし(問い合わせ先のみ明記) |
| 関西電力株式会社 | 2022年9月 | あり |
| 中国電力株式会社 | 2023年4月 | 専用ページはなし |
| 四国電力株式会社 | 2023年4月 | 専用ページはなし |
エリアの違いに加えて、企業によっては再生可能エネルギー由来の電源利用や省エネに関する副商材とのセット販売プランを設けるなど、各社で市場連動型プランの差別化を図っています。
市場連動型プランにまつわる、よくあるご質問
市場連動型プランのメリットは?
先述の通り、市場連動型プランでは季節や気温、時間帯によって電気料金が変動します。市場価格が低い時に電力を利用すれば、固定プランよりも安価に電力を利用できるというメリットがあります。
また、電力需要や市場価格の変動に合わせて電力使用のタイミングを調整することで、電力コストを抑えることも可能です。
市場価格は一日のうち、太陽光発電による供給量が多い日中の時間帯に下落することが多く、早朝や夜間では供給量が減少し価格が上昇する傾向があります。そのため、日中の稼働量が多い工場やオフィス入居の多いビルなどの契約ではメリットが得られる可能性が高くなります。
市場連動型プランのデメリットは?電気代の高騰リスクは?
一方、市場連動型プランでは市場価格が上昇すると、電力料金も高くなるというデメリットがあります。電力需給のひっ迫等による市場価格の上昇と、電気使用量が増えるタイミングが重なることで、電気料金が大幅に高騰してしまうリスクもあります。
最終保障供給とどちらがお得なの?
最終保障供給約款については「各エリアの大手電力会社標準プラン比1.2倍の単価」から制度が見直され、市場価格が上乗せされるようになりました。
参考:値上げ注意。 最終保障供給約款に契約する法人が気をつけるべきこと
加えて最終保障では市場価格が1円等に下落した場合でも、各エリアの大手電力会社標準プランの従量料金単価が下限値として設定されます。例えば、東京電力エリアの場合、月間平均市場価格が1円となった際も、適用価格は22.54円となります。

一方、市場連動型プランだと、市場価格が標準プランの単価以下に下落した場合には、比例して従量料金単価も下落するプランが多いため、主に価格下落傾向にある状況の場合には市場連動型プランのほうが最終保障約款よりもメリットが出る可能性が高くなります。
ただし市場価格が上昇局面の場合、どちらのプランでも従量料金単価は上昇するため注意が必要です。
まとめ
ロシア・ウクライナ問題による燃料価格の高騰、急激な円安により普及した市場連動型プラン。直近では燃料価格も一時期より落ち着いており固定単価メニューを再開する電力会社も散見されます。
市場連動型プランだと電源調達価格を販売価格に折り込めるため、電力会社としては燃料高の環境下でも取り扱いやすく、今後は各社メニューが増えていくと予想されます。
市場連動型プランで契約する場合、電気使用量の大小、使用する時間帯によって適用される単価や最終的な電気料金が大きく異なりますので、現在、契約中のプランの内容、価格水準と比較検討することが重要です。
また、電力会社の撤退等により最終保障供給約款での電力供給を受けざるを得ない場合、最終保障への市場価格反映が決定しており、電気料金の変動リスクが発生します。今後、市場連動型プランを扱う電力会社が増えてくることが考えられるため、各社プランの特徴をよく比較したうえで契約を検討することが重要です。
参考:最終保障供給とは? 制度の概要や料金、申し込み方法について解説
エネチェンジBizでは、独自の電気料金メニューを提供しています
制度変更を受けて値上げされた最終保障供給より、割安になる市場連動型プランを複数の電力会社で開始しています。料金メニューやリスクもご案内できますので、まずはお気軽に一括比較・お見積もりください。