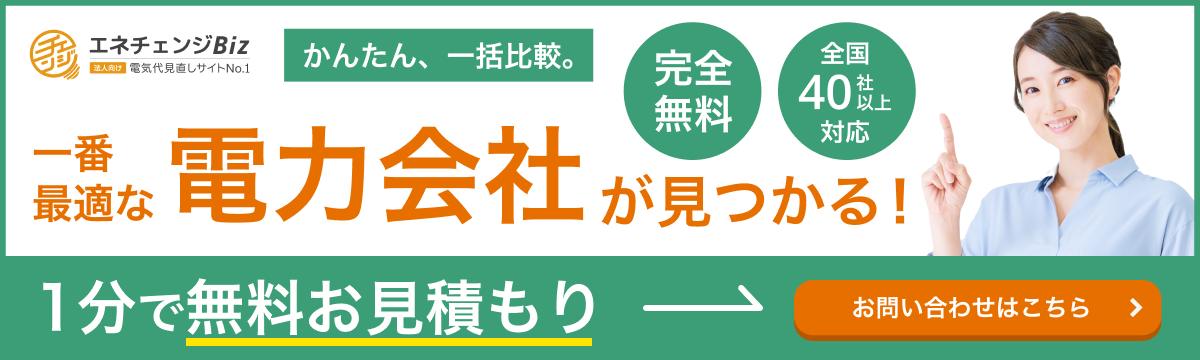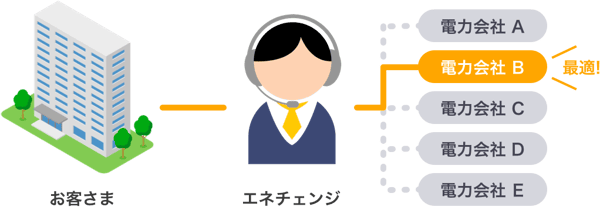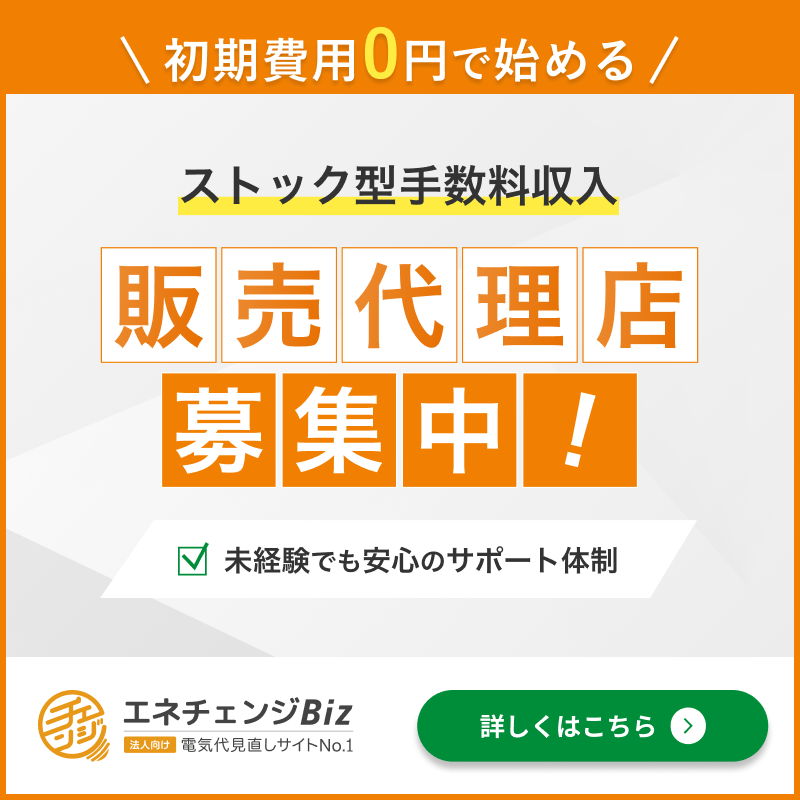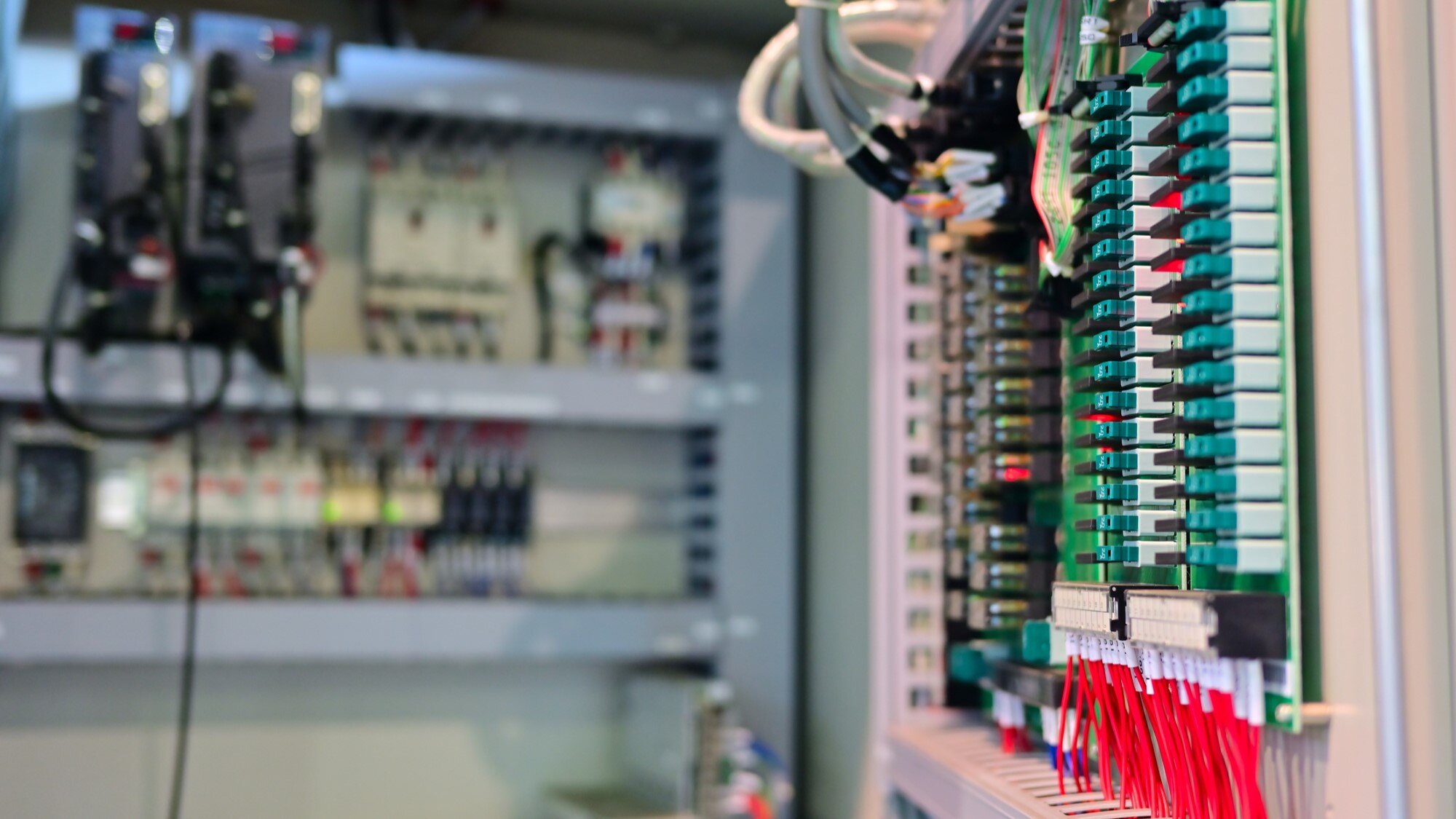
※編集部注:【2025年4月2日更新】
本記事は、最新の情報をもとに内容を一部修正しました。
自社施設の電力使用状況を知る上で、負荷率は重要な指標になります。より安い電力プランを探す際も、自社の電力使用状況に合った会社を探すことがポイントになります。電力プランとのマッチングの良し悪しを判断するために必須となる数値が負荷率です。
電力会社がより安い見積もりを出せるかどうかは、施設の負荷率の高低度合いによって大きく変わってくるからです。
本記事では、負荷率の基礎知識や計算方法、負荷率が高くなる施設と低くなる施設について具体例を上げながら解説します。記事を読むことで負荷率についての理解が深まり、電気代削減の助けになるはずです。
負荷率の基礎知識
負荷率とは、その施設が使用できる電力の最大容量(契約電力)のうち、実際にどれだけの電力を使用したかを示す割合のことです。
年単位を基準として月や季節ごとの差を把握したり、1日を基準として昼と夜の差を把握するために使われます。常に設備が稼働している24時間営業のスーパーや工場では負荷率は高くなり、夜は電力消費が少なくなる学校やオフィスビルでは負荷率が低くなります。
このように施設によって負荷率には大きな差があります。負荷率が高い施設ほど効率的に電気を使えていると言えるため、電気料金が割安になる傾向があります。逆に負荷率が低い施設では、電気料金は割高になります。
負荷率の計算方法
負荷率は、年・月・日ごとなど、一定期間における平均電力と最大電力の値を使って求められます。
- 負荷率(%)=【平均電力(kWh)/最大電力(kW)】×100
負荷率が高い例と低い例

ここでは、負荷率が高くなるケース・低くなるケースについて、具体的な施設例を紹介しながら解説します。
負荷率が高い例

負荷率が高くなるのは、24時間営業もしくは長時間稼働している施設です。例えば、24時間営業のスーパー、夜間や週末にも休みなく稼働している工場、総合病院などは負荷率が高い施設です。
このような施設では時間別の消費電力の変動が少ないため、時間帯と電力需要をグラフにすると高低差が少なくなだらかな形になります。
負荷率が低い例

負荷率が低くなるのは、一定の時間や期間中に人がいなくなり稼働率が大幅に下がる施設です。例えば、一定の季節にしか営業しないスキー場やプール、長期の休日がある学校などは負荷率が低い施設です。また、稼働時間が決まっている官公庁や工場でも負荷率は低くなる傾向にあります。
このような施設では時間によって消費電力が大きく変動するため、時間帯と電力需要をグラフにすると高低差がはっきりと表れます。つまり施設の負荷率が高いほど、電力を有効に活用できていると言えます。
日本の年負荷率の推移

国内の負荷率の水準は、1990年代には50%台で推移していましたが、2000年代以降、新型コロナ禍の影響があった2020年度を除いて60%を上回る水準を維持しています。
これは省エネ機器の普及・導入のほか、ピークカットやピークシフトといった負荷率平準化の取り組みが進んだことが影響しているためでしょう。
出典:資源エネルギー庁|第4節 二次エネルギーの動向
負荷率でみる、電力会社との相性
より安い見積もりを引き出しやすい電力会社は、自社の負荷率の水準によって異なる場合もあります。負荷率が高い施設であれば、東京電力や関西電力といった大手電力会社(旧一般電気事業者)で電気代が安くなる傾向にあると言われています。
休みなく稼働する負荷率の高い施設が対象であれば、電力会社の発電設備(石炭や原子力、一般水力など)の稼働率が高くなるため、発電コストが下がり値下げしやすくなるからです。
一方でスキー場や学校のように負荷率の低い施設であれば、新電力のほうが安くなりやすい、と一般的には言われています。
これは新電力は基本料金における価格競争力を出しやすい、と言われていることと関係があります。大手電力会社と違って、多くの新電力は自前の発電設備を保有していません。主に電力の卸売市場などから電気を調達しています。
つまり発電所の固定費がかからず、大手電力会社のように発電費用を基本料金に乗せる必要がないため、基本料金における価格競争力を出しやすい、という理屈です。
使用できる電力の最大容量のうち使用量が少ない、つまり負荷率の低い施設は、電気代に占める基本料金の割合が大きくなります。そのため新電力が価格競争力を発揮しやすい施設なのです。
実際にエネチェンジ Bizで新電力に切り替えた企業の電気代削減率を見てみると、負荷率が低い企業ほど削減率が高いことがおわかりいただけるでしょう。
| 新電力に切り替えた企業による電気代削減率(負荷率別) | |
| 負荷率 | 電気代削減率(平均) |
| ~20% | 25.2% |
| 20~40% | 16.5% |
| 40~60% | 11.9% |
| 60%~ | 11.4% |
ただ最近では電力の卸売価格低下の影響などもあり、新電力でも高負荷のユーザー企業に安い見積もりを出すケースも目立ってきました。電力会社を取り巻くビジネス環境によって、上記の傾向も変わってくるため、あくまで参考情報としてとらえる程度でよいでしょう。
法人向け電気代削減サービスのご案内
法人向け電気代比較サービス『エネチェンジBiz』は、一番安い電力会社が見つかる比較サービスです。削減額や信頼性など、ご希望に合ったプランを公平中立な立場でご紹介できます。
電気の切り替えで一番大変な「電力会社ごとの見積もりをとって、比較する」という部分を、電力に関する知識を持った専任担当者がフォローをさせていただきます。まずは「自社で切り替えた場合、どれだけ安くなるのか?」が分かる無料診断も実施できます。必要な情報は、毎月の電気代の明細書のみです。
電力会社の切り替えをご検討の方は、下記からお問い合わせください。専門スタッフよりご連絡を差し上げます。どうぞお気軽にお問い合わせください。