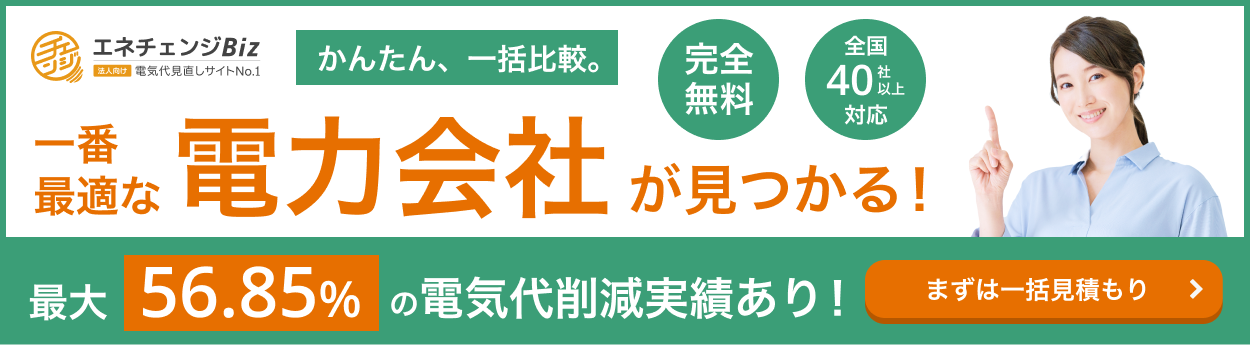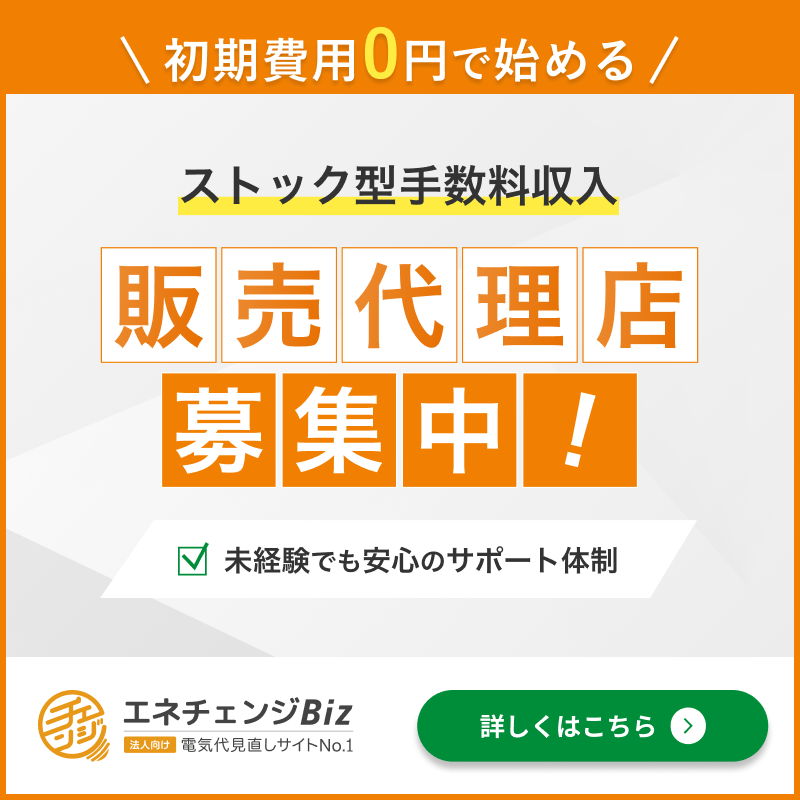地球温暖化が深刻な問題として浮上するなか、持続可能な未来を確保するためには、カーボンニュートラルの概念がますます重要となっています。
地球温暖化や気候変動といった環境問題に対処するために、今企業はどのような役割を果たすべきなのでしょうか。本記事では、カーボンニュートラルとは何か、なぜ重要なのか、どのように取り組んでいけば良いのか解説します。
カーボンニュートラルとは?

初めに、カーボンニュートラルに関する一般的な知識と概要について解説します。
カーボンニュートラルに取り組む目的と背景
カーボンニュートラルとは、地球上で排出される炭素排出量をゼロにする、あるいは排出される炭素量と同等の炭素を吸収することです。排出量から吸収量と除去量を差し引き、プラスマイナスを相殺することで、実質的なゼロを目指します。カーボンニュートラルに取り組む主な目的は、地球温暖化と気候変動に対処し、持続可能な未来を確保することです。
背景としては、地球温暖化が進行するなか、気候変動が人類や地球環境に与える影響がますます深刻化していることがあります。極端な気象現象や海面上昇などの問題が顕在化し、これらは生態系や経済、社会に大きな影響を与える懸念材料のひとつです。このような状況下で、地球温暖化を引き起こす主要な要因である温室効果ガスの排出量を極力削減し、最終的にはゼロにすることが求められています。
企業がカーボンニュートラルに取り組むことには、地球環境保全という大きな社会貢献以外にも以下のようなメリットがあります。
・企業ブランドイメージの向上
カーボンニュートラルへの取り組みは、企業の持続可能性へのコミットメントを示すことが可能です。これにより、消費者や投資家に対してポジティブなイメージを与えることができます。
・企業利益の向上
カーボンニュートラルへの取り組みを通じて、省エネルギーや再生可能エネルギーの導入など効率的なエネルギー利用につながるため、コスト削減から利益向上が期待できます。
・リスク管理の強化
カーボンニュートラルへの取り組みは、気候変動やエネルギー価格の変動などのリスクに対する企業の耐性を高め、将来的なリスクを最小限に抑えることが可能です。
・投資家の関心の引き付け
カーボンニュートラルへの積極姿勢が、ESG(環境、社会、ガバナンス)指標に関心を持つ投資家からの支持を獲得する可能性を広げ、資金調達や評価の面で優位に立つことができます。
カーボンニュートラルと脱炭素の違いは?
カーボンニュートラルは、直訳すると「炭素中立」で、二酸化炭素などの温室効果ガスの排出量と吸収量の均衡を意味します。一方、脱炭素は温室ガスの代表格「CO2」をゼロにすることが最終的な目的です。2024年2月時点で、脱炭素の明確な定義がなされていないため、カーボンニュートラルと同義に扱われることも多く見られます。
厳密には、脱炭素が排出量ゼロを目指しているのに対して、カーボンニュートラルでは排出と吸収によりプラスマイナスゼロと「実質的」なゼロを目指す点が異なります。また、脱炭素ではCO2に焦点を当てることが多いのに対し、カーボンニュートラルではメタンやフロンガスなど、その他の温室効果ガスを幅広く対象とする場合が多い傾向です。
更に、カーボンニュートラルの類語としては「ゼロカーボン」というものがあります。こちらも、地球温暖化に関連する温室効果ガス排出量の削減が目的ですが、微妙な違いがあることをご存じでしょうか。ゼロカーボンでは、植林などの管理によって温室効果ガスの排出量を森林が吸収する量以下に抑えることで、実質的な排出量をゼロにすることを目指します。
ゼロカーボンも「CO2排出量の実質ゼロを目指す」という点では、カーボンニュートラルに近しい概念といえるでしょう。
関連記事:脱炭素とは? 押さえておきたい基礎知識
参考:瀬戸内市|ゼロカーボンってなに?
参考:経済産業省|「カーボンニュートラル」って何ですか?(前編)~いつ、誰が実現するの?
参考:経済産業省|「カーボンニュートラル」って何ですか?(後編)~なぜ日本は実現を目指しているの?
企業が取り組みやすいカーボンニュートラルとは

ここでは、カーボンニュートラルについて特に取り組みやすい事例を2つ紹介します。
医療・介護分野における省エネへの取り組み
同社では、2002~2018年までISO14000を取得し、環境問題への対応を進めてきましたが2019年にRE Actionの取り組みへ転換しました。カーボンニュートラルに向け太陽光発電を行い、グループ内の太陽光発電による発電量は2018年時点で69万kW、2021年時点では76.6万kWに上昇しています。
しかし、まだ不十分なため、発電事業者から自然エネルギーの電力を長期に購入する契約「コーポレートPPA(C-PPA)」について、20年の契約期間での導入を決定しました。また、新規事業所における充電スペースの完備を進めながら、業務用車両を順次、電気自動車に転換しています。
更に、照明のLED化を推進するとともに、使い捨て製品について品目数で10%削減を達成し、省エネへの取り組みに励んでいます。
参考:伯鳳会グループ|医療・介護分野における「再エネ100%」への取り組み
製造分野における再生可能エネルギー移行への取り組み
2019年に自社での太陽光パネルによる自家発電が約20%、青森県横浜町の風力発電からの電力購入が約80%という組み合わせにより、再生可能エネルギー100%工場を実現。印刷業を営む同社では、サプライチェーン排出量の削減は範囲が広く、取り組みの苦戦が続いています。
そこで、カーボンニュートラル推進に向けて上流の材料メーカーや配送、下流の顧客を含むサプライチェーンを対象とした再エネ100%の達成やカーボンニュートラルへの取り組みについての勉強会を複数回開催しました。
その結果、製本加工会社1社が再エネ100%を達成し、インキメーカー2社が自社負担でカーボンオフセットを実施。更に、2023年には1社が「再エネ100宣言RE Action」への参加を宣言しました。中小企業のカーボンニュートラル推進の旗手として、サプライチェーン全体を巻き込んだ取り組みを現在も進めています。
参考:株式会社大川印刷|「風と太陽で刷る印刷会社」 ~サプライチェーンを巻き込んだスコープ3の削減~
省エネルギー対策の実施
省エネへの取り組みは、カーボンニュートラルへの貢献につながります。また、最終的にエネルギー消費量を削減し、企業運営コストの減少が図れる点は大きなメリットです。省エネに取り組む姿勢は、社会貢献意識を示し、企業イメージと消費者からの共感を高める効果が期待できるでしょう。企業が実施できる主な省エネルギー対策には、以下のようなものがあります。
参考:朝日新聞|省エネとは? 重要性や取り組み事例、企業・個人ができることを解説
・エネルギー効率の向上
機器や設備の効率化を図ることで、同じ業務を行う際のエネルギー使用量を削減します。例えば、省エネ型の照明設備やエネルギー効率の高い機械の導入、省エネ型の冷暖房システムの利用、LED照明への移行といった具合です。
・エネルギー利用の見直し
不要な機器類のスイッチオフや、冷暖房の適切な温度管理など日ごろのエネルギー利用の見直しにより、省エネを徹底していきます。また断熱材の適切な利用や窓の二重窓化など、建物の断熱性能を向上させることで、冷暖房の使用量の削減を図るのもひとつの方法です。
・再生可能エネルギーの導入
自社の発電設備に再生可能エネルギーを導入し、エネルギーの自給自足を図ります。太陽光発電や風力発電などが一般的な再生可能エネルギーの導入例ですが、もっとも着手しやすいのは太陽光発電パネルの設置です。国や自治体でも再生可能エネルギー普及のために、多くの補助金を提供しており、それらを活用することで実現しやすくなります。
・省エネ意識の向上と従業員教育
従業員に対する省エネ意識の啓発や、エネルギーの無駄遣いを減らすための行動指針の策定など、組織全体で省エネに取り組むための意識向上を図ります。小さなことの積み重ねが、大きな成果へとつながるため、軽視できない対策のひとつです。
再生可能エネルギーへの切り替え
カーボンニュートラルに向けた取り組みのなかでは、手間がかからない再生可能エネルギーへの切り替えが、すぐに着手できるため、おすすめです。企業にとって再生可能エネルギーへの切り替えには、以下のメリットがあります。
・経済効果
現在のエネルギー価格高騰を踏まえ、将来的に見ると今後は化石燃料よりも安定的で、安価なエネルギー源となる可能性があります。政府補助金・税制優遇措置を活用することで、導入コストを軽減できる点もメリットです。エネルギー自給率の向上により、エネルギー価格変動リスクを軽減できるうえ、災害時の停電リスクに対するBCP対策としても有効です。
・企業イメージの向上
再生可能エネルギーの積極的な活用姿勢は、企業としての環境への配慮をアピールできます。顧客や取引先からの評価を高められ、社会貢献意識の高まりにより従業員のモチベーション向上にもつなげることが可能です。例えば、「採用活動での優位性につながる」「投資家から注目され投資や融資の獲得で有利な条件となる」といったことも期待できます。
・社会貢献
中小企業であっても、世界につながる社会貢献が可能です。再生可能エネルギーの活用は、地球温暖化対策という大きな課題への貢献であり、地域社会のエネルギー問題解決にも一役買うことができます。中小企業におすすめの再生可能エネルギーとしては、以下のようなものがあります。
・太陽光発電:導入コストが比較的低く、設置場所を選ばない
・風力発電:発電量が比較的安定している
・小水力発電:小規模な事業所でも導入しやすい
・バイオマス発電:地域資源を活用できる
例えば、予算的に太陽光発電などが導入できない場合には、再生可能エネルギーにより発電した電力を供給している事業者からの購入という方法も選択肢のひとつです。電気を選択して買うことで化石燃料の消費量抑制に貢献し、カーボンニュートラル推進に役立ちます。
カーボンニュートラルに取り組む企業事例

カーボンニュートラルは、温室効果ガスを実質的にゼロにする点で現実的な考え方といえるでしょう。一方で、実際にどのように取り組むべきか着手方法がわからない場合もあります。そこで、ここではカーボンニュートラルに取り組むためのヒントを企業事例とともに紹介します。
国内企業のカーボンニュートラルの具体事例
・鉄道会社の事例
同社では、国内初のカーボンニュートラルを導入した「カーボンニュートラル・ステーション」を実現しました。年間で排出される二酸化炭素の約半分を再生可能エネルギーと省エネ効果による削減を実施しています。これらは、鉄道事業のなかでのカーボンニュートラル実現の好事例となっています。
参考:環境省|~日本初の『カーボン・ニュートラル・ステーション』~阪急電鉄 京都本線「摂津市駅」の開業にあわせた 阪急電鉄(株)との連携による地球温暖化防止メッセージの発信等について(お知らせ)
・セキュリティ企業の事例
同社では、2030年度までに温室効果ガスを45%削減とし、2045年までにはゼロとする目標を掲げています。同社の温室ガス排出の70%は、オフィスでの電力使用です。カーボンニュートラル実現に向けて、省エネ機器の導入や自社施設への太陽光発電設備の導入、グリーンエネルギー証書の購入による相殺効果を目指しています。
また、サプライチェーンへの説明会を開催し、情報の共有などグループ全体での取り組みを進めることにも尽力。2030年には、約9,000台所有する車両の100%をハイブリッド車などの低燃費車への移行を目指しています。
参考:セコム株式会社|地球温暖化防止
参考:セコム株式会社|サステナビリティ重要課題とKGI・KPI
・大手流通事業者
流通事業を行う同社では、輸送の際に排出される二酸化炭素の量を可視化し、企業のESG経営をサポートするサービス「エコトランス・ナビ」を活用。同サービスを通じて事業によって生じるCO2排出量が明確になり、課題の把握と改善策の検討を進めることに役立てています。更に、照明のLED化やエコドライブの奨励など、省エネ対策も推進中です。
参考: NIPPON EXPRESSホールディングス株式会社|脱炭素経営に不可欠なツール「エコトランス・ナビ Ver.2」
参考: NIPPON EXPRESSホールディングス株式会社|23回“物流環境大賞”受賞! 脱炭素社会やカーボンニュートラルの実現に最適なツール 「エコトランス・ナビ」 ※特許出願中(特許:2022-39597)
エネチェンジBizで最適な電力会社をみつけよう
エネチェンジでは、企業のカーボンニュートラルへの取り組みに関し、無料でのサポートを提供しています。再エネ導入や契約プランの見直しから、コーポレートPPAの実現に向けた支援まで、さまざまなサポートを行っています。
例えば、「トラッキング付FIT非化石証書」の交付もそのひとつです。トラッキング付FIT非化石証書は、再生可能エネルギーの普及促進のために設けられた「固定価格買取制度」の対象となる非化石電源によって発電された電気の環境配慮の価値を証書化したものです。発電に関する信頼性の高い証書として、注目されています。
エネチェンジでは、証書の交付と再エネ電源の切り替えの両方に対応しています。カーボンニュートラルに向けた取り組みをワンストップでサポートするエネチェンジをぜひご活用ください。